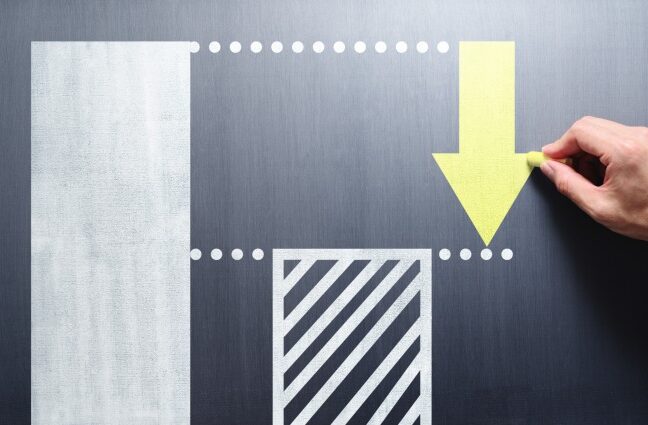
不動産投資をする際に活用したいのが「減価償却」です。減価償却費として経費計上することで、一定期間にわたり毎年の所得税を抑えることができます。本記事では、不動産投資において減価償却を行う仕組み、計算方法などについて分かりやすく解説します。
【著者】矢口 美加子
オーナーのための家賃保証
「家主ダイレクト」
こうしたお悩みを抱えている方は、まずは資料ダウンロード(無料)しお役立てください。
本章では、減価償却の考え方や仕組み、対象となる不動産投資用の資産について解説します。
減価償却とは、事業主が事業で使用する固定資産を、その資産の「耐用年数(※詳しくは後述します)」に応じた「取得価額」に分割し、経費計上する会計処理の方法です。
減価償却資産を取得した際にかかった費用は、その全額を取得した年の必要経費とすることはできません。その資産を使用できるとされている期間の全期間にわたり、分割して必要経費として計上していきます。たとえば耐用年数が10年という減価償却資産の場合は、10年間をかけて減価償却を行います。
「一定の価値がある資産は長期に渡って使われるのが基本であり、その価値は年数が経過するごとに下がっていき、最終的にゼロになる」というのが減価償却の考え方です。帳簿に記載する際は、まず購入したものを資産として計上し、その後は減価償却費として毎年分割して経費として計上します。
減価償却の対象となる事業用の資産は、建物・建物附属設備・機械装置・器具備品・車両運搬具などです。たとえば賃貸経営においては以下のような資産が減価償却の対象となります。
なお、10万円以下の資産は「消耗品」として一括で経費計上するのが一般的です。
減価償却資産を使用できる期間として、国が定めた年数のことを「法定耐用年数」といいます。法定耐用年数を使用すると減価償却費が正しく計算できるため、決算書への計上を適切に行うことができます。不動産投資に関連する建物と建物附属設備の耐用年数は、以下をご覧ください。
【住宅用の建物】
| 構造 | 耐用年数 |
|---|---|
| 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 | 47年 |
| 石造・ブロック造・レンガ造 | 38年 |
| 金属造 | 骨格材の肉厚が4㎜を超えるもの…34年 3㎜を超え、4㎜以下のもの…27年 3㎜以下のもの…19年 |
| 木造・合成樹脂造 | 22年 |
| 木骨モルタル造 | 20年 |
【建物附属設備】
| 用途 | 耐用年数 |
|---|---|
| 蓄電池電源設備 | 6年 |
| その他の電気設備 | 15年 |
| 給排水・衛生設備、ガス設備 | 15年 |
出典:国税庁 – 耐用年数(建物/建物附属設備)
法定耐用年数はあくまでも国が定めた基準であるため、品質に問題がなければ耐用年数を超えても使用できます。
不動産投資において減価償却費を実際に計算する場合、「定額法」「定率法」「簡便法」という方法のうち、いずれかを使用することになります。以下の流れで減価償却費を計算していきます。
1.建物の構造を確認する
2.減価償却率を調べる
3.減価償却費を計算する
それぞれの詳細について解説していきます。節税につながるため、しっかり理解していきましょう。
減価償却率は建物の法定耐用年数をもとに割合が決まるため、まずは建物の構造を確認します。たとえば、鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のマンションの耐用年数は47年ですので、新築で購入した場合は47年間にわたり減価償却することができますが、木造アパートを新築で購入した場合は22年間となります。
なお、中古物件を購入した場合は、耐用年数の残存期間で計算していきます。たとえば、築5年の木造アパートを購入した場合は
となりますので、減価償却できる期間は残り17年間です。ちなみに土地は建物と違い劣化しないため、減価償却はできません。
次に、減価償却資産の償却率を調べます。減価償却率をまとめた表は以下をご覧ください。耐用年数ごとに償却率が記載されているので、定額法・定率法それぞれの償却率を割り出してください。
ここで注意したいのが、建物を取得した年月日です。定額法の場合、平成19年4月1日以降に取得したものは償却率が違うため、取得した年度の償却率を採用します。たとえば平成25年に取得した築10年の木造アパートを定額法で減価償却する場合は、耐用年数の残存期間が12年となるため償却率は0.084です。
一方、定率法は、取得日が「平成19年3月31日以前」「平成19年4月1日~平成24年3月31日」「平成24年4月1日以降」で償却率に違いがあるため、取得した年月日のものを選びます。
なお平成28年度の税制改正において、平成28年4月1日以後に取得する「建物附属設備」と「構築物」の法定償却方法については、定率法が廃止され定額法のみとされていますので注意しましょう。


出典:国税庁 – 減価償却資産の償却率等表
定額法、定率法、簡便法の計算方法を紹介していきます。
定額法は、償却費額が原則として毎年同額となる計算方法です。計算式は以下です。
取得価額とは、建物を手に入れる時にかかった費用で、建物の購入代金や仲介手数料などが該当します。ケース例として、以下の条件で定額法を用いて減価償却の限度額を算出してみます。
以下の計算式で算出します。
毎年184万円ずつ減価償却費として経費計上できるため、22年後には法的な資産価値はゼロとなります。
定率法は、償却費額が初年度ほど多くなり、年数が経過するにつれて減少する方法です。ただし、定率法の償却率で計算した償却額が、償却保証額(償却すべき最低限の金額)に満たなくなった年分以後は、毎年同額となります。
ケース例として、以下の条件で定率法を用いて減価償却の限度額を算出してみます。
定率法は以下の計算式で計算します。
当てはめて計算すると以下になります。
償却率をかける金額が減少するため、年数が経つほど減価償却額が少なくなっていきます。
中古物件を購入して不動産投資をする場合は、法定耐用年数ではなく、事業に使用可能な期間として見積もられる年数で計算することができます。耐用年数を算出する方法として、以下の2パターンが挙げられます。
| ➀法定耐用年数を超えている | 法定耐用年数の20パーセントに相当する年数 【計算式】 耐用年数=法定耐用年数×20% |
| ②法定耐用年数を超えていない | 法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に、経過年数の20パーセントに相当する年数を加えた年数 【計算式】 耐用年数=(法定耐用年数-築年数)+築年数×20% |
たとえば法定耐用年数を超えている場合のケース例として、法定耐用年数は22年、新築から30年以上経過した中古木造アパートの見積耐用年数を計算すると、以下になります。※端数は切り捨てるので4年となります。
【耐用年数を超えた場合】
次は耐用年数を超えていない場合で計算してみます。法定耐用年数が22年で、経過年数が10年の中古木造アパートを簡便法で計算すると、見積耐用年数は以下になります。
【耐用年数を超えていない場合】
2.経過年数10年の20パーセントに相当する年数
→ 10年 × 20% = 2年
3.耐用年数
→ 12年 + 2年 = 14年
このケースでは耐用年数が14年となります。
不動産投資においての減価償却の計算を具体的にシミュレーションしてみましょう。令和2年に購入したと仮定し、新築と中古それぞれで定額法を用いたケースで紹介します。
新築の建物からシミュレーションします。以下の条件で計算していきます。
計算すると以下になります。
→新築マンションの場合は、法定耐用年数となる47年間は毎年154万円を減価償却費として経費計上できます。
中古の建物で計算していきます。条件は以下です。
最初に法定耐用年数を計算します。築年数が法定耐用年数をすべて経過していない場合、耐用年数は以下の計算式で求めます。
計算すると以下の耐用年数となります。
法定耐用年数は39年のため、償却率は0.026です。以下の計算式で計算します。
→築10年の中古の建物という場合、法定耐用年数である39年までは毎年182万円を減価償却費として経費計上できることがわかります。
減価償却費を経費として計上することにより、➀実際の支出がないのに経費にできる、②損益通算により節税できる、という2点のメリットを得られます。それぞれ解説します。
減価償却資産の場合、実際には支払いがないにもかかわらず経費計上できるのが大きなメリットです。購入した建物の代金を一括で経費として計上せず、耐用年数の期間内のみ一定金額を経費として計上します。計上した金額は所得から差し引けるため、課税対象額が少なくなり、節税効果を得られます。
損益通算とは、同一年分の利益と損失を相殺することです。サラリーマンなどが不動産投資をする場合、給与所得と、投資用不動産の運用時に発生する不動産所得の利益と損失を相殺できます。
たとえば、給与所得が800万円、不動産所得が300万円で他に所得がない場合、総所得金額は1,100万円です。仮に不動産所得が300万円の赤字ならば、損益通算により総所得金額は500万円になりますから、課税対象額を低くでき、所得税を安くできます。

出典:国税庁 – No.2260 所得税の税率
では、減価償却を使用するとどのくらい安くなるのか紹介します。以下は、減価償却を使用しない場合の計算式です。
課税対象額:1,100万円×33%ー153万6,000円=209万4,000円
減価償却費を使用しない場合、所得税額は209万4,000円です。
次は、減価償却費を使用した場合です。以下のように計算します。
課税対象額:1,000万円×33%ー153万6,000円=176万4,000円
減価償却費として計上する場合、所得税額は176万4,000円です。減価償却をしない場合の所得税額は209万4,000円だったため、33万円を節税できることになります。
不動産投資で減価償却費を経費計上すると節税効果がありますが、一方で注意しなければならない点もあります。大きく考えられる3点について紹介します。
減価償却資産は耐用年数を過ぎると減価償却が終わるため、費用計上ができなくなります。そのため、会計上は利益が増えることになり、所得税が上がります。所得税が増えると手元に残る資金が少なくなるため、キャッシュフローが悪化する可能性があります。
デッドクロスとは、「ローンの元金返済額が減価償却費よりも多い状態」のことです。キャッシュフローは変わりませんが、税務上では大きな利益が出ていることになり、税金が高くなってしまいます。これは、節税目的で古い木造物件を購入する場合によく見られるケースです。
この状態になると、帳簿上は利益が出ているのですが実態とは違いがあるため、資金繰りの悪化が懸念されます。デッドクロスを避けるには、以下に挙げる対策を購入時に行っておくと良いでしょう。
・残存耐用年数が長い新築や築浅の物件を購入して、減価償却期間を長くする
・購入時に自己資金を多く入れる
・元金均等返済を選択する
減価償却期間の終了までにローンを完済すれば、デッドクロスが起こる可能性は低くなります。自己資金を多めにして購入すると返済金額が少なくなるため、ゆとりのある返済が可能です。また、一定の元金を返済する元金均等返済を選ぶこともひとつです。毎年元金の返済額が増えていく元利均等返済に比べると、デッドクロスの発生を遅らせる、あるいは防ぐことができます。
売却時の譲渡所得税が高額になるリスクも挙げられます。たとえば、6,000万円で取得したアパートがあるとします。同じ金額で売却した場合、売却益がゼロなので譲渡所得税はかからないのではないか、と感じるかもしれません。
しかし、減価償却をするとアパートの会計上の価値が減少するため、最終的な価値と売却価格に差額が発生していきます。差額部分に対して譲渡所得税が課税されるため、年数が経過するほど税額が多くなるのです。
減価償却を利用して大きく節税効果を得られるのは、「木造・軽量鉄骨造の住宅」と「耐用年数切れの物件」です。
大きな節税効果を得るには、1年ごとの減価償却費が大きいものほど有効です。木造の減価償却費は22年、軽量鉄骨は27年と比較的短いため、短期間で償却できます。1年ごとの償却金額が大きいため、所得を抑える効果が高いのです。
また、耐用年数切れの物件も償却期間が短いため、新築よりも節税効果が高いといえます。
不動産投資で減価償却費を経費計上すると、所得金額を圧縮できるため、所得税を抑えることができます。ただ、減価償却をしていくごとに会計上の価値(簿価)が下がっていくため、売却時の譲渡所得税が高くなる可能性があります。不動産投資で減価償却を活用する場合は、あらかじめメリット・デメリットをよく確認しておくようにしましょう。

宅地建物取引士、整理収納アドバイザー1級、福祉住環境コーディネーター2級の資格を保有。家族が所有する賃貸物件の契約や更新業務を担当。不動産ライターとしてハウスメーカー、不動産会社など上場企業の案件を中心に活動中。