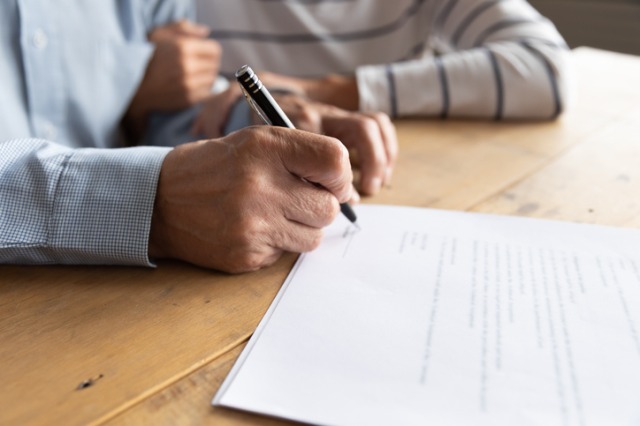
賃貸契約書を締結する際に目にする「特約条項」。一般的に記載されている内容や、有効とされる内容の条件など、特約条項についての正確な知識を持つことはオーナーが入居者とのトラブルを未然に防ぐためには大切なことです。縁あって所有物件の入居者となった相手と良好な関係を保つために、あいまいになりやすいポイントは特約条項にしっかり明記していきましょう。
【著者】水沢 ひろみ
オーナーのための家賃保証
「家主ダイレクト」
こうしたお悩みを抱えている方は、まずは資料ダウンロード(無料)しお役立てください。
賃貸借契約書とは、オーナーと入居者の間で賃貸契約を結ぶ際に取り交わされる契約書で、双方が署名・捺印することで有効になります。この賃貸借契約書には賃貸借契約に関して必要な情報が盛り込まれており、以下のような内容が記載されるのが一般的です。
「特約条項」とは、これらと並んで賃貸借契約書に記載されるもので、オーナーが特に取り決めておきたい内容を盛り込むことができます。オーナーとしては、後の負担やトラブルを避けるために、できるだけ有利な特約を盛り込んでおきたいと思うかもしれませんが、どのような内容でも無制限に許されるというわけではありません。
そこで、この特約に関してどのような取り扱いがなされているのか、どのような特約を付けるべきなのかなどについて、以下に解説していきます。
賃貸借契約書には、前章で紹介した一般的に記載される内容のほかに、オーナーが入居者との間で特に取り決めておきたい内容を特約条項として記載することができます。
法律上は「法律行為を行う当事者間の契約内容は自由に決められる」というのが原則ですので、オーナーは賃貸借契約を行うにあたって希望する条件を自由に盛り込むことができます。
ただし、法律に反する内容や、一般的な道徳観念に反し、社会的な妥当性を欠くような内容の契約を行うことは認められません。また、特約条項として記載する内容は、あいまいな内容や表現を避け、当事者同士が誤解する恐れがないように注意する必要があります。お互いにあいまいな理解の下に契約をすると、後日思わぬトラブルを招くリスクがあるからです。
では、特約条項にはどのような内容を記載すればよいのでしょうか?賃貸借契約書に記載されやすい特約内容を以下に紹介します。これらはオーナーと入居者との間の解釈の違いなどで、特にトラブルに発展しやすい事柄といえますので、特約として明記し事前に確認しておくことが双方にとって大切です。
原状回復に関するトラブルは、入居者とオーナーの間で頻繁に生じやすいもののひとつです。金額が高額になることもあり、裁判にまで発展する事例が多数ありますので、特に注意が必要です。
原状回復に関しては、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を定めて、基準を示しています。このガイドラインでは、入居者の故意や過失、善管注意義務違反(※)、その他通常の用法を超えるような使用法によって生じた損耗や毀損については、入居者の負担としています。一方、経年変化や通常の使用によって生じた修繕のための費用は、オーナーが負担するべきとしています。
そのため、入居者との原状回復に関するトラブルを避けるためには、入居者自身の故意や過失、不注意、通常と異なる使用法によって生じた損害については、入居者に負担を求めることを特約条項として明記しておくとよいでしょう。
入居者が退去する際のハウスクリーニングに関する取り扱いもトラブルになりやすい内容のひとつですので、賃貸借契約書の特約条項として明記しておくことがおすすめです。
前の入居者が通常の用法で使用していたとしても、新しい入居者に貸し出せるようにするにはハウスクリーニングが必要となることが多いものです。しかし、国土交通省のガイドラインによると、通常の清掃を超えるクリーニング費用は、オーナー負担が原則とされています。
そのため、このクリーニング費用を入居者の負担とするには、賃貸契約書にその旨を記載しておかなくてはなりません。
また、クリーニング費用を入居者が負担するという特約があったとしても、支払時期、金額が明確でない場合、当該特約は無効となります。
ですので、
などを明確に定めて契約書に明記するとともに、入居者に対してしっかりと説明する義務がありますので、クリーニング費用に関する特約を設ける際には注意が必要です。
賃貸住宅は、部屋同士の距離が近く、生活音やにおいなど、ほかの部屋からの影響を受けやすい環境にあります。本人は気を付けているつもりでも、周りの人がストレスを感じている可能性があります。そのため、入居者同士がお互いにルールを守って生活し、近隣の迷惑になるような行為は控えることが常識です。
しかし、入居者の価値観はさまざまであり、入居中に控えて欲しい行為については賃貸借契約書に明確に記載しておくとよいこともあります。
よく見られる利用制限や利用禁止事項としては、下記の内容があります。
楽器の使用は近隣への騒音トラブルの元になる可能性がありますし、ペットの飼育は鳴声による騒音だけでなく、臭いの問題や、部屋が傷むという問題も生じます。また、石油ストーブの使用は火事の恐れがあることから、禁止しているオーナーは多くいます。
SOHO利用を許可すると、居住者以外の人間の立ち入りが多くなるなど、ほかの入居者への迷惑となる可能性もあります。建物内での喫煙は、壁紙が変色したり、ベランダなどを通じて隣の部屋に煙が入ったりするなどのトラブルになるリスクがあります。そのほか、ごみの捨て方のルールを守るといった内容も、近隣への迷惑とならないように大切なことのひとつです。
このような利用制限や利用禁止に関する特約は、賃貸借契約書に具体的に明記し、入居者へ注意喚起しておくことが有効だといえます。
中途解約や短期解約に関する特約も、明確に定めておきたいことのひとつです。
中途解約とは、一般的な契約期間である2年間が経過する途中で解約する場合をさし、「契約を解約する2カ月前までには解約の申し出をしなくてはならない」などと定めるケースが多く見られます。
一方の短期解約とは、契約から一定期間以内の短期間で解約するケースです。どの程度の期間を短期とするかはオーナーごとに異なりますが、6カ月未満、1年未満、2年未満などと一定の期限を設けて、その期間内に解約した場合には一定の違約金がかかると取り決める場合があります。
入居者が退去することが決まった際には、オーナーはできるかぎり空室の期間ができないように次の入居者を探す準備をしなくてはなりません。そのためには早めの退去予定である旨の連絡が必要であることから、中途解約の規定が必要となります。
また、募集広告費用やクリーニング費用などを支払ったり、敷金・礼金をゼロにしたり、フリーレントをつけたりするなどで入居者募集をしても、数か月などといった短期で解約されてしまうとオーナーは経営が成り立ちません。そこで、短期解約の規定を設けて、短期で解約する際には違約金を課すことにしてバランスをとるケースが増えています。
こういった取り決めをする場合には、解約を申し出る期間がいつまでなのか、違約金がかかる期間はいつまでなのかということに関する特約を、明確に定めておかなくてはなりません。
賃貸借契約が満了した後も入居者が部屋に住み続けたい場合には、契約更新の手続きをする必要があります。その際に、オーナーは入居者から更新料を受け取ることが慣例になっていますが、この更新料は法律で定められたものではありませんので、更新料を受け取るのであれば賃貸借契約書にその旨と金額を明記しなくてはなりません。
なお、賃貸借契約書を作成する際には、自動更新条項を付けるケースが一般的です。自動更新条項とは、賃貸借契約の期間が満了する前の一定期間までに、貸主・借主のどちらからも契約終了の意思表示がない時は、その賃貸借契約は更新されることになるという内容を契約書に盛り込むことです。ただし、この自動更新条項がなくても、
上記に該当する場合、当初の契約と同じ条件で契約が更新されたとみなされるという法律の規定があります(借地借家法26条、28条)。これを「法定更新」と呼びますが、法定更新となった際に更新料の請求が認められるかどうかについては、裁判上の判断も分かれています。
ですから、法定更新の場合も、更新料が発生する旨の記載がないと法定更新時に更新料を請求できなくなる可能性が高くなることに留意し、更新の種類に関わらず更新の際には更新料が発生することを契約書に記載することをおすすめします。
また、毎月の家賃の振込手数料は、別段の特約がない限り入居者の負担となるのが原則ではありますが、あらかじめ賃貸借契約書に明記することで、居者とのトラブルを避けることができる可能性が高まります(※民法485条によると、別段の意思表示がないときは、弁済の費用は債務者の負担とするとされています)。
反対に、敷金の返還の際には、滞納している賃料や原状回復の費用などを差し引いた残額から振込手数料を差し引いて返還することが一般的ですが、この場合にもその旨特約に記載しておくようにしましょう。
先程も説明したように、特約の内容はオーナーが自由に決められるのが原則です。しかし、あまりに法律やガイドラインからかけ離れていたり、オーナーの利益に極端に寄っていたりするなどの場合には、特約の内容自体が無効になる可能性があります。
賃貸借契約を巡っては、さまざまなトラブルが起こる可能性がありますので、トラブルを避けるためには、問題になりそうな事項は特約条項にしっかりと定めておくことが大切です。特約条項の有効性が心配なオーナーは、専門家へ相談することで問題のない賃貸借契約書を作成するようにしてみてください。
賃貸契約書の特約条項の意味や特約として記載される内容、特約の有効性などについて解説しました。賃貸経営において大切なことは、物件が空室になることを避け、満室の状態を維持することだといえます。
しかし、賃料の不払いがあったり、近隣に迷惑行為を行ったりするような入居者であれば、かえってリスクになるだけです。また、原状回復費用やクリーニングの費用、更新料、振込手数料など、お金に関することについてあいまいにしたまま契約することはトラブルの元となります。ぜひこの記事を参考に、賃貸借契約書の特約条項に関する理解を深め、トラブルのない賃貸経営を目指してみてはいかがでしょうか。

かつて銀行や不動産会社に勤務し、資産運用に携わった経験を活かし、現在は主に金融や不動産関連の記事を執筆中。宅地建物取引主任、証券外務員一種、生命保険募集人、変額保険販売資格など保険関係の資格や、日商簿記1級など、多数の資格を保有し、専門的知識に基づいた記事の執筆とアドバイスを行う。